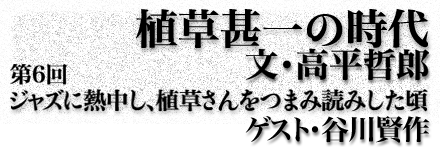|
谷川さんのお父さまの谷川俊太郎さんも義兄・小野二郎の親しい友人だった。義兄がまだ三十前に、最初に務めた出版社の弘文堂から芸術叢書シリーズで谷川氏の本も出版している。初対面の谷川賢作さんは「おとなしいタイプのジャズマン」の雰囲気をバッチリ出していた。大岡玲さんとも逢ったと言うと、大岡家と谷川家は親交があって、以前は正月になると大岡家に行ったものですと賢作さんは話してくれた。
■はじめは譜面も読めなかった
音楽の方をやるって決めたのは、高校出てからです。大学には行かないで、そのまま防衛庁の真ん前にあったアン・ミュージック・スクール・オブ・なんとかコンテンポラリーというところに行きました。初年度は、当時高柳(昌行)さんのグループに在籍していたコウセイケンジさんっていう人に、ガチガチのバップを習ったんです。それまでぼくはロック系で、ディープ・パープルとかのコピー・バンドをやっていて、譜面も読めませんでした。もう全部みんなが集まって耳でコピーして、全部その通り模倣ですね、最初から最後まで全部模倣。芸大に入るだけの力がないのはわかっていました。だから先生について勉強したかったんですね。
もうジャズは下火だった。コルトレーンはいないし、マイルスは別方向に、すでにジャズ界にはスターがいなかった時代だ。
ただ、まだいろんな情報が新鮮でした。いきなりロックからジャズですから、ジャズに関して趣味っていうのがなかったんです。もう最初は先生の言うとおりに、おとなしく、レッド・ガーランド、ウイントン・ケリー、ハンク・ジョーンズ、トミー・フラナガンから入りました。バド・パウエルとビル・エヴァンスっていうのは、難しいからちょっと別格にランクされてるんですよ。まだお前ら、なにも弾けないんだから、まず左手からだ。右手はぜったい弾くなって言われて。右手は、ホーンとかギタリストのシングルトーンのソロなんだから、それにいたるまでに左手のサウンドっていうのは全部、いまからリスティングするからね。おもしろい先生だったんですよ。
延々と最初の三、四カ月は左手のコード・ボイシングだけやって、それから今度ブルースのリフです。エリズバンスとか、フォープリバーグとか、そういうのを右手で全部。今度は左手を入れないんですよ。このメソッドはたいへん楽しかったですね。ジャズって、最初聴くとわからないって、よく言われますよね。ほんとわからなかったですけど、やっぱりシンクロして、自分がピアノを練習するに従って、見えてくるっていうのがすごく新鮮でした。
その当時いちばん好きだったのはレッド・ガーランドです。よく聴きました。非常に明快なんですよ。『グルービー』、最高ですよね。あれの「Cジャム・ブルース」からやっぱり入りましたからね。
ぼくはその当時、もうジャズを聴いていなかった。それこそ当時、谷川さんが熱中していたジャズは高校生のときに聴いてたものだ。
■植草さんとの出会い
植草さんの文章と出会ったのはいくつぐらいのとき?
やっぱり同じぐらいです。父と祖父が、もうなんだか迷路のような、すごく巨大な書庫を持っているんです。そこに、ビニール・コーティングの晶文社の本(『スクラップブック』)がずらっとありまして。出会ったといっても、全部つまみ食いです。ジャズとミステリーと……まぁ、ほんとにつまみ読みだったんですよね。すごく読みやすい文体で、こうなんか時間を忘れて読みました。
その一枚のレコードなり一曲なり、一冊の本でも、もうすっと、これおいしそうだなぁっていう書き方なんですよねぇ。
植草さんも含めて、十八、九ぐらいのときに、一瞬にしてジャズが谷川さんのもとへ押し寄せてきたようなものですね?
はい、本当にそうです。そのころ、文京区の小石川図書館で週に五枚レコードを貸してくれたんですね。そこに毎週入り浸ってました。せっせとカセットにダビングして。それが嬉しかったです。せっせと(ジャケットの)裏を写して。千枚から千五百くらいあったんじゃないですかねぇ。CDはないです。それと、当時はまだまだジャズ喫茶があって、ぼくは、高円寺南口の『ランプシャー』とかに出没していました。でもジャズ喫茶って八〇年代になると、軒並み減ってきましたよね。
■ジャズ喫茶での勉強
谷川さんの時代だと、例えばジャズ喫茶で「静かにしてください」なんて紙なんて、出されないでしょう。
まだそういうところに、つるんで行きましたね。『ランプシャー』なんかはそうですね。でも、ロック喫茶と二軒並んでいたんで、ロック喫茶の音がかすかに聴こえちゃうんですよ。
谷川さんは、いまの時代、ジャズ喫茶がなくなったっていう実感はありますか?
はい。『ランプシャー』もないですし『木馬』ももうないですよね。新宿の『DUG』は残ってますけれど……。当時、学校のネットワークが大きくて、沖縄の出身のジャズのピアノ科だったピアニストとかドラムの人とか、沖縄の人たちとくっついていたんです。―世代上の人たちだったんですけど、子分格で入れてもらっていて。「ちょっと賢作、一緒に行こう」って言ってね。「じゃ『ランプシャー』にいまから連れて行ってやる。おまえ、開けた瞬間から違う店だからな、肝に銘じとけよ」って言われて(笑)。「きょうは俺がこれ聴くから、お前なんか、ベイシーとかエリントンとか聴いてないだろ、だめだなぁ」とか言われて(笑)。「お前ピアノばっかりまじめに先生に言われたとおりにやって……きょうは俺が聴かしてやるから、とにかく喋んなくていいから黙って勉強に来い」って言われて。ガシャンと開けてね。で、その先輩がこんにちはって言って、ツーカーみたいで。店の人はもう萎縮しちゃって。「じゃぁベイシーのなんとか」って。「次にエリントンのなんとか」って三曲か四曲ぐらいリクエストしちゃって。「いいから、コーヒー入れてきて」って店の人に。「おまえ感想とか言うな、店出たら聞いてやるから」(笑)。そういう思い出あります。ほんとうに、いい先輩でしたね。
ぼくらの世代っていうのは、最初勉強したのはマッコイ・タイナーとエルヴィン・ジョーンズとかそういう音楽だったんですけど、実際コンサートよく行って見ているのはフュージョンとか、クリスター・ダット、リー・リトナーとかで……。、そのあとで、エルヴィンなんかを見ているんです。ドラム・セットでも、タムタムが三つも四つもあって、シンバルがワシャッていうのを見慣れているんですけど、エルヴィンのセット見たら、タム二つ、シンバル二枚でしょう(笑)。それでもうぼくは、はぁーっと唸る唸る唸る唸るっていう。だから逆にカルチャーショックをうけたというのかなぁ。
いまジャズを聴いてる若い人も、やっぱり遡るんでしょうね。まぁ、ガーランドの話したんですけど、ガーランドは逆に新譜がね、ギャラクシーというレーベルから出て、聴くとがっかりしちゃうんですよ。音がぜんぜん違っちゃって。よくなってるんですけど、なんか、へんで、これガーランドの音じゃないなっていう。
■ピアニストとしての最初の仕事
『ディーバ』は二年ですね。いろいろ渡り歩いてきたわりに、ぼくはジャズの業界のなかでは、名が知られていないんですけど。アレンジとか作曲もやってました。
最初にやったピアニストとしての仕事は、南浦和のクラブというかキャバクラですね。アン・ミュージックの掲示板に、ちっちゃい紙でピアニスト募集って出ていたんですよ。そうしたら事務員の人がね「ちょっと谷川さん、これやらない? なんかちゃんと金出るらしいよ」って。ぼくはまだ『枯葉』と『サテン・ドール』と『ブルース』の三曲しか弾けないって言ったら、「いいんだいいんだよ、こんなもん、いっちまえば勝ちだ」ってね(笑)。いやー、いまではあんな仕事ないでしょうね。
それで、のこのこ行ったんですよ。駅前の五階建てのビルにある、ちょっと秘密クラブ的な店で、ベーゼンドルファーのピアノがガーンと置いてあるんです。ベースとドラムとサックスはすでに決まってたんですよ。そうしたら「なんか弾いてみなよ」って言われて、ガチガチに緊張しちゃいまして。「実は申し訳ありません。『枯葉』と『サテン・ドール』と『ブルース』しか弾けないんです」「いいよいいよ、それいいじゃん、そんだけ弾きなよ。大丈夫だよ。あとはね、練習。道場だと思っていいから。来る客で俺が気にいらないやつは、お引きとり願っちゃうから」って言われて(笑)。それで、一日五ステージ、月曜日から土曜日まで、それで月給で九万。(笑)とんでもなく安いギャラで。でも、最初に行った体験っていうの、大きかったですね。
曲もいっぱい覚えました。千一(ミュージシャンが使うスタンダード・ナンバーのリフとコードが載った楽譜集)持ってきて、毎日二曲ずつぐらい。蓋あけたら、なんのことはない、ベースもドラムもね、同じくらいだったんですよ。奴ら、人が悪いからね。俺たちは大丈夫だみたいな顔、最初はしてたんだけど、セッション終わったあとに「実はさ、おれらもさ、同じようなところなんだ」って(笑)。そこで一年半くらいやらしていただいて、自分でいうのもなんですけども、メキメキっていう、もうすごい楽しかったですね。
とても気持ちのいいミュージシャンなので、インタヴューアーであることを忘れて、このあとひとりでジャズの話をしてしまった。ジャズの話をきちんとするのも久し振りだった。そんな話が出来たのも、ぼくより十四歳下の谷川賢作さんも植草ワンダー・ランドの住人だったからだ。
|