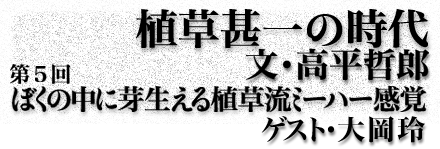|
数年前、母校武蔵高校の英語の矢崎先生に会う機会があった。「大岡君知ってる?」「どこのですか?」「高平君の後輩になるんだけど。お父さんが大岡信さんなんだけど」「はいはい、大岡玲さん、彼、武蔵なんですか?」「きみみたいに、学校の授業より好きなことがあったみたいで、本ばっかり読んでいたよ」……。大岡信さんと義兄・小野二郎は、同じころ、明治大学で教鞭を執っていたこともある親しい友人だった。義兄は大岡さんの本も編集して出版している。矢崎先生から後輩だと知らされた直前に、ぼくの『スタンダップ・コメディの研究』の本の書評を大岡玲さんが書いてくれたこともあって、不思議な巡り合わせに驚いてしまった。数日後、大岡玲さんに連絡を取って、ぼくの出版記念会に来てもらう約束をした。当日、初対面
の挨拶をして、五分も経たないうちに旧知の仲のような会話を始めていた。「高平さんのことは、子供のときから、父から小野さんが弟の話ばかりするんだってことで、いつも聞かされてました」……だから、この日、初めて一時間に渡って話をしたときも、叔父が甥に昔の話を懐かしんでしているような気にさせられた。
■植草さんとの距離感
大岡さんが、最初に植草さんのものを読まれたのは、『スクラップブック』ぐらいからですか?
ぼくが植草さんに初めて出会ったは、『スクラップブック』の前です。七二、三年から『話の特集』で読んでまして。ただ、植草さんっていうふうに意識してないわけですよ。なんかこう「洒落たこと言う小父さんがいるな」という意識でした。
ただ、植草さんには大変申し訳ないんですけど、その当時、ニューヨークとかアメリカ文化って、アメリカ映画は大好きだったんですけれど、その他については軽蔑するとこがあったんです。どちらかというと、感覚的にイタリアとかフランスとか、ヨーロッパの方が好きだったんですよ。ただ、映画だけなぜかハリウッド・オンリーで、植草さんの前のバイブルは、小林信彦さんの一連のものでした。アメリカの文化で形作っている、ユダヤ系の文化における映画みたいな、そういうものって結構好きだったんだけど、ニューヨークとかってそんなに興味無かったんです。ところが植草さんがそういう文章を書いてらして、それでもって「ふーん」なんて思って読んでいたわけです。あとはハードボイルドもすごく好きで読んでいて。あれはサンフランシスコとか、西海岸が舞台のものがわりと多いじゃないですか。それなのにもかかわらず、なんであんなにアメリカを嫌っていたのかなあ……。
ニューヨークとかアメリカに対する偏見って、親父の影響だったと思うんです。親父は国文出て、詩人なんかやってましたけど、ほんとうはフランス文学がすごく好きで、ヨーロッパかぶれしているわけですよ。それで、「ニューヨークなんてのはあれは田舎だ」ていうふうなことを聞かされていて。だけど田舎なのに、なんで植草さんみたいにああいうおもしろい小父さんが、ニューヨークにそんなおもしろ味を感じるんだろう。あるいはアメリカっていうものの細かいところに興味を感じるのかっていう思いがあったんですよ。
だけど、なんかどっかでいつも、植草さんに距離があって。すごくおもしろい、すごくそこに行きたいと思うのに、なかなか近づいていけない。植草さん流の「気取り」っていうか、おもしろ味っていうか、好奇心とか、ああいうものにすぐポーンと入っていけないという感じがすごくあったんです。だから、そういう意味で言うと、中間、中途半端な距離感を、植草さんに対しては、いつも感じてました。
■植草さんとの接点
植草さんの観る映画って偏っているでしょう? ぼくも西部劇、ミュージカル、それからまあ広く言ってアクションで、コメディーだから、植草さんとの映画の接点っていうと……ない(笑)……そこがすごく不思議なんです。
ぼくが植草さんのコラムを読むようになったのは、ちょうど植草さんがニューヨークに入れ込み始めるころだったんです。だから逆に、植草さんがフランスの映画をほめてたりすることとか、ぼくがわりと好きだったハリウッドの、言ってみればいかにもハリウッドらしい馬鹿馬鹿しい根っ子のないものやミュージカルは、あまり好まれていない様子というのが、すごく不思議な感じだったんですよ。ニューヨークのなにが好きなんだろうって……。
ニューヨークに行かれてたら、きっとジャズいっぱい聴いて、芝居観て、映画観て……ってそう思いますよね。でも毎日本屋に行って本ばっかり買ってらしたんでしょう。その印象がすごく強いんですよ。グリニッジ・ビレッジあたり歩いて、オモチャを探してるっていう、そういう印象がすごく強くて、何なんだろうなっていうね(笑)。
どのくらい買ってらしたんですか?
「えーと…ダンボールでね六十ぐらいですか」
「ええっ?!」
「マンション、もうひと部屋借りたんだから」
「(笑)信じられない。だけど、それ全部読まれたんですかね」
「いや、全部は読んでないと思うな。ただ買っとかないと不安、ていうことだったんじゃないのかな」
■植草さんの存在感
当時ぼくなんかアメリカのもの、たとえばエド・マクベインのシリーズなんかでも、植草さんが新作ものを書評したりするじゃないですか。そういうのを見て、買いに行くようなところはありました。でも、自分で読んでみると植草さんみたいな見方がどうしてもできないんですよ。それが、また自分でなんか不思議でしゃくにさわってね。だいたいぼくはいまでも粗雑で、わりと大づかみに見ちゃうところがあるんですけど、植草さんってほんとに、たとえばエド・マクベインの87分署シリーズに、猫かなんかを灰にしている犯人の話がありますけど、そういう猫の灰みたいなこと、細かなことに異様にこだわって、そこから話が展開していくんですよね。
映画でいうと、ヨーロッパの映画って、いつも我慢して観てたってのがあって。最近だんだん自分と同世代とか、ちょっと上ぐらいの監督が出てきて、そういうのおもしろがって観るようになりましたけど……昔アントニオーニの作品なんて結構我慢して観てましたよ。なんで俺こんなとこで我慢してるんだろうみたいな。アンゲロプロス監督の『旅芸人の記録』とか、みんなほめるじゃないですか。ぼくは、あれ、ずーっと寝てて(笑)。ああいうのを観て植草さんだったらたとえばどうなふうに思って、書いただろうかって、想像するとおもしろいですよね。
植草さんが世間に与えた影響ってなんでしょう?
いま、ぼく自身が書評をするときに、植草さんの影響をうけているのは感じるんですよね。昔だったら絶対そんなふうに見ないで、なんかわりと俯瞰図的に見てたのに、いま、他のこと全部、その本の重要なプロットとか全部すっとばして、小物のところに異常に執着してそこだけ書いたりとか。そういうことやった瞬間、「あれーっ」とかって思うことは結構あります。
植草さんの文章って特徴がありますよね。一時期、植草さん的な文体が多くなったり、そのあと随分たってから、椎名誠さんや嵐山光三郎さんもそうですけど、そういう文体が出てきたときに、やっぱり植草さんのあたりで地盤が変化しちゃったのかなって思いましたね。
植草さんの話し言葉ふうな文章はそう簡単に真似できるもんじゃない。だがあの当時『宝島』でハガキ一枚の形で、文章を応募したことがあった。それを読んだ片岡義男、津野海太郎が全部に目を通
して文章のレベルの高さに驚いていた。大半が話し言葉調だったが、こうした文章を手軽に書いてしまうのはラジオの投稿の投稿の文章が母胎になっているんだという結論になった。そういう文章が定着して書くことの怖さを考える前に、文章を書けるようになってしまったのではないか。
ぼくが小学校の高学年ぐらいから、深夜放送がすごく盛んになっていって。それからちょっと経って、今度『ぴあ』が創刊されたんですよ。当時『ぴあ』には「はみだしぴあ」っていうのがあって、ああいうとこに投稿してくるのも、深夜放送とかに投稿してくる投書とほとんど同じだったですよね。そういうところに、1行ぐらいで上手いことを書く人がいて。ぼくなんかそういうことあまり出来なかったんで、「エライ上手い奴らがいるんだなあ」なんて感心してたのを、はっきり覚えています。
植草さんの文章にも、いつもその感じがあって。さっきちょっと距離があったってふうに言いましたけど、いまごろになって植草さん流の独特なミーハー感覚っていうのが自分の中に非常に根強く芽生えてきてるのを、すごく感じるようになってきました。
植草さんがいなかったら、七〇年代後半から八〇年代にかけてのサブカルチャーの大きな流れは、やっぱりありえなかったかもしれないって思うと…デカイ存在だったなって、あらためて思います。
|