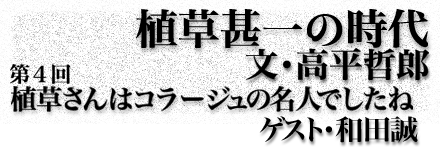|
高校時代に『殺人(マーダー)』の一部を『11PM』で見て、こういうものが見たかったという気がした。その後、『話の特集』の読者だったので、和田誠さんには特別
な興味があった。この雑誌で川端康成の『雪国』の書き出しを、野坂昭如や植草甚一のパロディでやったときも、こういうものが見たかったという気がした。初めて挨拶をしたのは植草さんにコンサートで紹介してもらったときだったのかもしれない。雑誌『ワンダーランド』でも、和田さんにイラストレーションを依頼したことはあったが、ぼくが初めて和田さんと話せたのは、『宝島』の二年目で七四年のことだった。このとき、山下洋輔さんに初めて逢って、ヨーロッパ・ツアーの話を三十枚で小説にすることを依頼した。初小説に快い返事を貰って、その足で和田さんの事務所に行って、その挿絵を依頼した。憧れの人ふたりに同じ日に逢えたのだ。その後、フリーになってからある雑誌で対談をすることが二回ほどあって、ちゃっかり和田さんと親しくお付き合いさせてもらうことになった。ぼくの本も何冊か装幀してもらっているし、イベントのポスターなども数多くお願いしている。ミュージカルと映画とジャズの師匠でもある。
■植草さんがくれたイラストレーション
植草さんに初めて会ったのは六〇年だと思う。草月アート・センターで、草月ミュージック・インっていうのやっていたでしょう。そこに聴きに来ていたんですね。
武満徹さんとか、寺山修司とか、いろいろなジャンルの人たちが俺たちも一緒にやりたいっていうので集まっていた。ジャズと現代音楽と大きく分けて別々なんだけれど、ぼくは両方行っていましたし、植草さんもそうですね。あのころわりと、なんでも物珍しくて。
実際運営していたのは、そこの草月アート・センターというところに常任でいる谷口さんという人が現代音楽の会(『コンテンポラリー・シリーズ』)を、奈良さんという人がジャズの会(『草月ミュージック・イン』)を担当していたんです。あのころ、草月会館がなにか若い人たちの寄り合う場所としてとてもよかったという感じなんじゃないでしょうか。
その奈良さんが、まだ学校を出たばっかりのぼくをつかまえて「君はジャズが好きらしいから、ミュージック・インの方のポスターをやってくれないか」っていうんで、ぼくはもう大喜びで引き受けたんです。それで、ポスターも作るっていうこともあって、必ず行ってたんですよ。そこで奈良さんが植草さんに、「この子はきっと出ますよ(笑)、イラストレーターの卵で、ジャズも好きでよく来てるし、ポスターも頼んでいるです」というふうに紹介をしてくれて。それで次の月から植草さんは、必ず外国の雑誌のイラストレーションのおもしろそうなのがあると切り抜いて袋に入れてくれるんですよ。
渋谷に「恋文横町」ってありましたよね。その中にアメリカの放出雑誌屋さんがあったの。ぼくは多摩美の学生だったんだけれども、いまみたいに洋書が気軽に買えるわけじゃなかったし、外国のイラストレーションを見るチャンスがあまりなかった。それで『エスクァイア』とか外国の雑誌を見に行くわけ。ぱらぱら見て、間に一枚、ベン・シャーンがあると、その一冊だけ買って帰るということをぼくはしてたのね。だからベン・シャーンとかスタインベルグとかを探すために、ずっと1ページずつ見ていて、結構長いこと、その本屋にいるわけ。そこで何度か植草さんと会いました。
そのころの植草さんは、ジャズや映画や文学なんかの好きな記事があると一冊買って、でも、本がたまってしょうがないから、買った日にいらないページはどんどん破いて捨てちゃって、必要な記事しかとっておかないっていうスタイルだった。それでその捨てるべきイラストレーションなんかをぼくにくれたわけです。もう一人、イラストレーターの真鍋博さんがやっぱり草月の常連で、真鍋さんには真鍋さんで、植草さんの判断で、これは和田くん向き(笑)っていうふうに分けてくれてました。どっちかっていうと、固い真面目な絵を真鍋さん、漫画っぽいのはぼくにっていうふうに分けて、それぞれ袋に入れて。二つ袋を毎回持ってきてくれて、二人にくれてた。一九六〇年っていうと、まだ植草さんが五二歳? いまの、ぼくよりうんと若いわけね。うーん、やっぱり昔の人のほうが立派だったな。
イラストっていう、略語になったのは、六〇年代の中頃からじゃないですかね。ぼくはいまだに「イラスト」っていうのはあんまり好きじゃないので「イラストレーション」って言うんだけれども……。六四、五年に、ぼくや横尾忠則や灘本唯人さんとかが集まって、『イラストレーターズ・クラブ』を作ったの。そのころまだあまり知られてない職業だったし、雑誌で仕事しようなんて思っても、挿絵画家という人たちが頑張っていたから、なかなかぼくらが入り込む余地がなかった。まだ雑誌編集者なんかも、イラストレーションもイラストレーターもあんまり知らなくて、じゃあ少し認知させなきゃいけないっていうんで、グループ作ってね、結構売り込んだりしたんですよ。
■いっぷう変わった映画評
和田さんがライト・パブリシティにいながら、よその仕事をなさったっていうのは入社何年目ぐらいからですか?
すぐです。給料もらいながら、別のところで稼げば、なんだあいつはっていう話になるんだろうけれども、ぼくがやっていたのは、まず日活名画座で、これはただです。洋画のポスターずっとやっていた。ライト入って即始めたんですよね。それからしばらく経って、草月ミュージック・イン。これはね、少しお金くれたと思うんだけど、微々たるもんだったと思います。それから『話の特集』が始まって、これもずっとただだから(笑)。ただどころか、ちょっと金足んないからいくらか寄付しろみたいな。『話の特集』にかける時間は非常に多かった。あまり会社のなかでおおっぴらにほかの仕事もできないので、目立たない小さなカットなんかを書いてましたね。
中学一年のとき『アボット・コステロ』とか『ターザン』とか、初めて大人の映画を観た。それで、映画っていうのはものすごいいいもんだと思って、プログラムを買って帰ったんですよ。立派なプログラムでした。いまのものより薄っぺらくて印刷も悪いけれども、執筆人がすごいんですよ。たしか植草さんが原作者について書いていたような気がする。あとは淀川長治さんが書いていたし、双葉十三郎さんも書いていた。そうそうたるメンバーがひとつのプログラムの中に入っているわけですよ。植草さんは映画が専門っていうよりは、どちらかっていうと、外国文学に詳しい人っていう感じだったですよね。でも、映画雑誌を読んでいると、植草さんしょっちゅう登場するし、それから外国から、例えばヒッチコックが来ると、ヒッチコックを囲んでみんなで食事をするようなときに、写真必ず写ってましたね。若いころの植草さんの風貌は、我々がよく知ってる髭のヒッピーおじいさんみたいのよりも、もっと小太りの髭の生えた紳士という感じでしたね。
植草さん、若いころに、築地小劇場が好きでよく観に行ったってエッセイに書いているんですよ。ぼくの父親がね、築地小劇場の創立メンバーなんですね。効果なんだけど。で、植草さんに聞いた話なんだけれども、その築地小劇場のスタッフが築地で芝居が終わって、ぞろぞろ銀座の方に出てきて、お茶飲んだり酒飲んだりするんだって。それよりさらに若い、一世代下の植草さんがそのスタッフのあとをついてきて、それで一緒の店に入って、築地の連中の話をずっと横で聞いてたってんだって。その中に君のお父さんもいたよなんて言ってくれて。親父に、そんな話聞いたけども覚えてるって聞いたら、ぜんぜん覚えてないって(笑)。
一九六〇年ぐらいの『映画之友』の評論を読まれて他の映画評論家と比べて異質な感じはしました?
したした。ちょっと、なんか他の評論家とは角度が違うっていうのかな。植草さんは、原作を読んじゃうからね。その原作者が他にどんな作品を書いているかとか、それが映画になったことはあるかとかっていうふうな角度でくるからおもしろかった。外国雑誌の記事紹介はあまりなかったけど、むしろ、そういう知識を、もう一回自分のフィルターに通して書くというような、そういう書き方をしていたような気がする。ぼくはファンでしたね。淀川さんは映画評論家というよりも『映画之友』の編集長としてのイメージが強いですね。その時代の映画評論家って言うと双葉さんと野口久光さん。それぞれやっぱり評論家にも、タイプっていうか、得意なジャンルがあって、野口さんはもちろんミュージカル評論ですよね。ミュージカルとアニメーション。アニメーションについて書くと、やっぱり相当詳しかったですね。植草さんは外国文学からミステリー系のものが得意でしたね。
■コラージュの名人
雑誌『ワンダーランド』の責任編集をなさるっていう話を聞いたときは、どう思われました?
いや、それは別に。ぼくは、『話の特集』を手伝っているだけの意識だから、自分が編集者というか、出しているっていう気持ちはなかったので。だから、むしろ興味あったし、楽しみにしていた。新聞活字を使った大判の雑誌のレイアウトは画期的っていうかすごくよかった。例えばまだ寿屋時代に出していたサントリーの『洋酒天国』とか、ときどきおもしろい雑誌が世の中に出るんですよね。ぜんぜん異質だけど、『血と薔薇』とかね。高平さんがいた『トランヴェール』なんていうのは、歴史の中で記憶に残る雑誌ですね。でも『宝島』はおもしろい雑誌だったよねぇ。植草さんがどれくらい本気でかかっているかっていうのが、わからなかったけど。
六〇年代から七〇年代にかけて植草さんが及ぼした影響というのは?
まず、ジャズを専門的ではなく、ジャズの歴史のなかでジャズを捉えるというよりも、もっと自分との関係において、感覚的に書くっていう、あの感じがやっぱりいちばん新鮮だったような気がします。そっちのほうからジャズファンを増やしたんじゃないかっていうふうに思う。散歩なんかはぼくは感じなかったけれども、あとはね、ちょっと不良っぽいところ。不良っぽいっていうか、不良っぽいところを紹介する。例えば『2001年宇宙の旅』を観ながらドラッグをやると、どうなるかみたいなことを書いちゃうんだよね。あのへんがおもしろかった。
コラージュは名人ですよ。すごい名人。それからああいうビジュアルのおもしろさっていう、こういうものがおもしろいよっていう、発見するのすごくうまかったし、自分がもの作るのも相当おもしろいじゃない。それから、いつもサインしてくれるじゃない。あれなんかもね、おもしろいっていうか、上手だったよね。作品が作品として成立してると思う。ぼくの知ってる、コラージュの名人が三人いて、一人は横尾忠則、一人は山城隆一、一人は植草甚一だって、なんかにちゃんと活字で書いたことありますね。ぼくはあまり上手じゃない。なんか理に落ちちゃうっていうか、やっぱり意味つけちゃうんじゃないかな。だからおもしろさがないですね。伸び伸びしてないっていうか(笑)。植草さんのは伸び伸びしてますよ。大入り袋からコラージュやっているのなんかおもしろかったなあ。
ハージベルトも植草さんから教わったんじゃないかしら。アル・ハージベルトっていう、主にブロードウェイの似顔絵描く人。ぼくらは映画のひとたちの似顔絵で先に知っていたんだけど。それで、ハージベルトっていうサインがしてあるんだけど、その他に隠し文字で、ニーナっていうアルファベットがどっかに隠されているなんて、ぼくは知らなかったから。それは植草さんから聞いてね。自分の娘なのね、ニーナって。それを髪の毛のなかとか洋服のしわとか、そういう中に書くんですよ。
植草さん、急にロックが好きになったことがあったね。あるときね、話しててね、「いまはジャズじゃなくてロックだね」って言って。だれかがね、新宿駅の雑踏を歩きながらね、人がいっぱいいるんだけど、なんか看板かなんか、これがマイクとすると、誰だったかなぁ、ミック・ジャガーっつったかなぁ、彼はこういう歌い方をするって言ってね、雑踏の中でやって見せるんだよねぇ(笑)。そんなことがあったなあ。
|