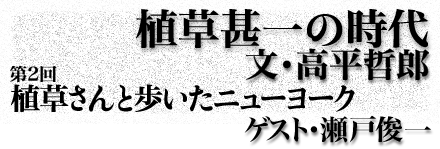|
■植草さんとの出会い
瀬戸さんは晶文社に入社して、植草さんの本を担当してから最後の『スクラップ・ブック』まで編集している。まさに植草付きの編集者で、植草さんは三度目のニューヨーク行きに同行させている。
そもそも瀬戸さんが晶文社に入った動機は、都筑道夫さんの本を編集したかったからと聞いているけれど。
いや、動機というのは『ぼくは散歩と雑学がすき』なんです。中学生の頃から『映画の友』の映画評は読んでいたので植草さんのことは知っていたんですよ。『話の特集』の連載が始まったのがちょうど大学生の頃です。ぼくはジャズにはあまり興味がなくて、少し聴いたりしたけれども、『スイングジャーナル』を毎月読んだりとかそういう感じじゃなくて。『ジャズの前衛と黒人たち』が出たときには、ジャズに関しては出たなっていうぐらいしか思わなかった。だから『話の特集』の記事を集めた『散歩と雑学』の方が印象的でした。
入社試験の作文で『散歩と雑学』の読み方みたいのを書いたんです。何書いたか憶えてないんですけどね(笑)。その作文が会社にとってあるのを見つけて、持って帰った。残しておくとやばいと思って(笑)。
植草さんのおもしろいところですか? そうですね、人がどうでもいいっていうような細かい事にこだわるところかな。それと『話の特集』やり始めた頃なんかは、映画とかジャズとかじゃなくて、街の話みたいな結構変なものがおもしろくて。
学生時代は、ミステリーもよく読んでいたんですよ。ミステリーに関しては『宝石』で植草さんを知ってて。だから、植草さんが映画評論、ジャズ評論のほかにミステリー評論をやるってことは良く知ってたんです。
ぼくが植草さんの担当になったのは、『ワンダー植草・甚一ランド』からです。あれは、ぼくが入社した時には既に進行していたんです。植草さんはゲラを見てなかったのか、もうほとんど見終っていたのか、よく分かりませんでしたが、はじめてお目にかかったのは、胃の手術のあと病院へお見舞いに行ったときです。写真で知っていた植草さんとはずいぶん違って見えました。
『ワンダー植草・甚一ランド』は割とデザインが主体の本だったから、その作業の手伝いをしたのが主で、植草さんとの交渉ってのはあんまりなかったです。よく会うようになったのはその後の『雨降りだからミステリーでも勉強しよう』(一九七二年九月)からですね。
ただぼくは、植草さんのところには原稿取りに行って待ってるなんてことはあまりなくて、何処か行くから、散歩に行くから付いてこいって、そういう感じで会ってましたね。
原稿は出来上がって、それ以外の用事でしょ(笑)。
植草さんのとこに行くのは、お手伝いに行くのがほとんどだったような気がします。引っ越しの手伝いなんかもありましたしね。
■ニューヨークで荷物持ち
植草さんとニューヨークに行ったじゃない?あれどれくらいの期間行ってたの?
一ヶ月。隣り合わせの部屋でした。ぼくを一緒に連れていった目的は荷物持ちですから、午前中に本屋行くんですよ、で、午後は別の本屋に行って、植草さんが本を見てる間にどっか近所ブラブラしたりとかしてました。それと植草さんの奥さんが一緒に行ったから、奥さんとちょっと街を観光したりとかそういう感じかな。ときどき植草さんが見たいとか言って映画に行ったり。夜は自由時間だったけど、どこも夜出て行くところがわからなくて。だから、夜は何人かと会ったりはしたけれど、それ以外は映画館に行ったりしたくらいですね。
朝は植草さんが起こしに来るんですよ。 ぼく寝起き悪いから…… (笑)。朝は、そのホテルで、食事です。コンチネンタルスタイルっていうの? ペストリーと珈琲とジュース。それが取り放題って言うんで、それですよ。昼はハンバーガーとか、ハンバーガーでもハワード・ジョンソンとかああいう注文取りに来るところ。その程度のもんですね。要するに簡単な料理。夜は、何回か外へ食べに行ったけど、ほとんど部屋へ持って帰って食べました。ホテルの向かい側にデリカテッセンがあって、そこでサンドウィッチ作ってもらって、チキンとか果物買って、持って帰って植草さんの部屋で皆で食べるんです(笑)。
「うわぁ〜キツイなぁ。じゃあさ、イタリア料理食べたとか何とかって無いの?(笑)」
「ないない(笑)。ほら植草さんの趣味、なんだっけ、イギリス風のパブとかそんなとこ行ったり。あとは、ロフトとかジャズ聴きに行ったりとか」
「ジャズは聴きに行ったの?」
「ええ、でも四月でジャズのシーズンじゃなかったので何回かですね。セシル・テーラーがホイットニーミュージアムでリサイタルをやっていました。そういうときはテープレコーダーを持たされて、録音させられるの。時間を見計らってカセットを入れ替えるのが役目でした」
ニューオリンズジャズとか聴きに行ったんですよね。それはニューオリンズ料理のレストランなんですよ。たしかあの頃、雑誌の『宝石』から取材費を貰ってるんですよ。それで、ニューヨークのジャズとか原稿を一応書いてたわけ。で、そのニューオリンズ料理の店に行って、日本から来て取材して文章書いてるんだって言ったら、そこがずいぶん気前よくてタダにしてくれて。そこぐらいですよね、まともに食事しながら音楽聴いたのは。
本屋はとにかく大好きなのが一軒あって、午前中必ずそこに行くんですよ。午後は顔馴染みとか二、三軒かな。一回入るとやっぱり三時間とか。新しいのが来たら全部見るわけですよ。だから毎日行くところは毎日とっといてくれるんですよ。新しいヤツを箱に入れて、まず一番に、入荷したヤツを見せてくれる。ジャンルは割とないんですよ。とにかく買うのが多いのは小説ですよね。あと写真集も買ってた。あとその店では、石版画とか、本から取ったヤツね、ああいうの一枚一枚バラして売ってるんですよ。割と安いんです。それを買って、解剖図とか鳥の絵とか、切り抜いてコラージュの材料にする。その場では切り抜かないけど、植草さんがそうするの知ってるから、本屋さんが「もったいない」とか言うんだけど……。
夜はコラージュ作りなんかして。それからあとはね、本のカードを作ってるんですよ。一日二、三百冊買うじゃない、それ一枚一枚タイトル書いて何処で買ったとか書くんですよ。で、夜終っちゃいますよね。
■植草式ニューヨーク散歩術
いや、そんなにキツイ毎日だって知らなかった。俺なら「午後はちょっとぼく用事がありますので」って言って逃げちゃうだろうな(笑)。
ちょっと遠くまで行こうかと思って、ちょっと言いかけたら、「一人で行くのは難しいですよ」とか言われて……(笑)。あと植草さん、その頃写真に凝ってたんですよ。それで荷物持ちをして撮影に付いていかされてた。だから本屋行って、その後は写真撮りに方々歩いてたんです。ちょうどホテルの前に、写真屋があったんです。一日中撮影して、夕方そこへ預けて、翌朝それが上がってきて見られるっていう。一日、二、三本じゃないかな。乱写していたわけじゃないですね。まだ当時はピント合わせマニュアルでしょ。だから、素人はたくさん撮れないですよ。
芝居を見ようとかは言わなかったですね。植草さんはミュージカルには興味無かったですし。映画はひと月一緒にいた間に十本ぐらい見たから三日に一回は行っていた。新しい映画です。四月は、ちょうどアカデミー賞の発表前だから、結構評判になってるのがやってるんですよ。ぼくが行った年は『ジュリア』や『結婚しない女』が候補になってました。ほとんど新しいやつっていうか、自分の知ってる監督の新作があると行こうって。そういう感じでしたね。映画の情報は『ヴィレッジ・ヴォイス』で調べていたんじゃないですか。それといつも行ってる古本屋の親父さんが植草さんの好きそうな映画を教えてくれて。
あとはね変な物を買うんですよ。それこそね変な物を探して。午前中に本屋へ行って、見る本がなくなるとブラブラ歩いて、今日はあっちの方行ってみよう、こっちの方行ってみよう……おんなじような物をよく買ってるんですよね。
今日初めて細かい話を聞くと、ひどいディレクターについたテレビ局のADみたいで、ちょっと悲惨だな。
それほど夜まで忙しいわけじゃないから自分の見たい映画に行ったりはしました。自分での買い物時間ってのはあまりないですね(笑)。本とかは、一緒に行ってるときに買ったけど、あとはあまり買わなかった。何時にどこで待ち合わせとか言うんですよ。さすがに、ずっとそこで待ってろとは言わない(笑)。だから何時にどこで待ち合わせみたいな、どこかでお昼食べようとか。もちろん奥さんが一番大変なんです。奥さんは本屋のなかで椅子に座ってるんですよ。四月だとまだ寒いんですよね、室内でも。その本屋っていうのは広くて暖房の無いようなところだから、コート着て、こう座ってるんですよ。奥さん、言いたいことは言うけど、そういう時はただ座って待ってる。植草さんには文句は言ってるんですよ。部屋で待ってるっていうのがイヤなんでしょうね。
レコード屋は、その時はあまり行かなかった。植草さんって面白いのは、向こうに着いてすぐに質屋に行って、プレーヤーを買ったんです。レコード買ってすぐに聴くつもりなんですね。でも、レコードを買った憶えあまり無いんですよ。まず最初にプレーヤーと、それからちょっと経った頃にスライドプロジェクター買って……。だけど、結局レコードは買っていない。買う前にまず本屋とブティックで満腹になっちゃうんですね。たぶん植草さんの好きな中古レコードとかが、それほど大きな店がなかったんじゃないですかねえ。ビデオとかそういう道具買うの好きでしたから。カメラもずいぶん買っていたし。
当時ビデオがあったら恐ろしかったでしょうね。情報が無いのがかえって良かったんですよ、きっと。今だったらインターネットやってるでしょ。誰かが全部設定させられて(笑)。
植草さん、あといろいろ楽器持っていたでしょう。それも高いのじゃなくて変な物を質屋で買うんですよ。そんなたくさんじゃないけど、クラリネット持っていましたよ。あまり高そうじゃないヤツで、それも安かったから買ったんじゃないかと思うけど。吹くわけじゃないんだけど、そういうもんつい買っちゃうんですよね。
■植草さんのスクラップブック
本の話でよく言ってたのは、経済学の本以外は何でも買うんだって。よく古本屋で教科書とか買うんですよね。教科書の古いヤツ、書き込みとかしてるヤツとか、あんなの別に読むつもりじゃないんだろうけど……。
いろいろなことを知ってるように受け取られていたけれども、植草さんコミックなんかはそれほどくわしくはなかった。ただ、全体的にそういうものが日本に情報が無い頃だったから……。『ぼくの大好きな外国の漫画家たち』はネタ本が何冊かあって、あとは新聞とかから取っている。結局、雑誌の場合はほとんどネタがあって書く原稿なわけで、植草さんの書き方はそれが上手いというか、読ませる書き方をするんですよね。
自分の書いた物にもそれほど関心がないんですよ。たとえば、コラム集めた『こんなコラムばかり新聞や雑誌に書いていた』を作ったとき。あれは細かい新聞のコラムをスクラップブックにいろいろ貼ってあるものがもとになっているんですが、これ植草さんの文章じゃないなって言うのがあるんですよ。各国の文学の話とかあるわけですよ。植草さんはアメリカ文学、イギリス、フランス文学の話はしますけどね、でもときどき変わったのが入ってるんですよ。ロシア文学についてとか。ぼくはちがうと思うんだけど、それが一緒に入っていても何にも言わないから、いいのかなぁって思って。ゲラのチェックもあまりしないですしね。もちろん本人にはゲラ見せて赤入れて貰ってるんだけど。新聞の無署名のコラム原稿あるでしょう。植草さんスクラップ好きだから、自分の原稿と自分の興味のあるのと一緒に貼っちゃうんですよ。それで何かちょっと混ざってんじゃないかって気がするんですけれど……。その頃はまさかそんな事あると思ってませんからね、ぼくも。後になってそう思ってるわけ。でもそれで文句言った人いませんから、まだ。いいんでしょうけど(笑)。植草さん書いちゃったのあまり気にしないんじゃないのかなと思って。
■植草式整理術
それと『中間小説時評』、あれは面白かったですよ。要するにその月の小説全部を読むんですよ。まず雑誌ばらすところから始めて。その作業自体が楽しいんですよね。ばらして連載をまとめたりとか、いろいろやっていました。そういう子供みたいな事を一生続けた人なんですね。
池波正太郎さんとの出会いも『中間小説時評』で、それまで、池波さんを読んだこと無い。日本の作家ってほとんど読んだこと無いわけですよ。だから、池波さんも、植草さんにとってはフランスの新人と同じわけなんです。それを、植草さんの独特の褒め方で書いて、池波さんっていうのも江戸っ子だから、そういうとこ分かるんでしょう。そうすると気が合って仲良くなったんじゃないですか。
『中間小説時評』書いてた時、植草さんの予定表が面白いんですよ。段ボールに赤や緑の鉛筆やマジックで書かれた閉め切りの予定表。きっと、あれ作るのが面白いんですよね。だから毎日作ってました。
亡くなってから整理するとノートが一杯出てきたんですよ。表紙にタイトルだけ書いてるノートって一杯ありましたよね? 中身が無くて。とにかくちゃんとした整理はしないけど、構想を立てるのが好きだったなのかな。ぼく、植草甚一式ってどこかで書いた事あるけど、紐と荷札で梱包してあるんですよ。それが植草式整理術。でも植草さんの家で一回どっかに仕舞っちゃったら出てこないんですけど。
六〇年代から七〇年代にかけての、植草さんの位置というのは、客観的にどういう風に見ますか?
かなり時代の象徴だったんじゃないですか。今だったらどうなんでしょうね。あの頃はとにかく他にそういう人がいなかったから。ジャンルが広いっていうのと、変わった格好して受ける人もあの頃いなかったですよね。植草さんはどの程度意識してたかわからないけど、ああいう形でマスコミに出た文化人っていうのは初めてだったんじゃないでしょうか。
|