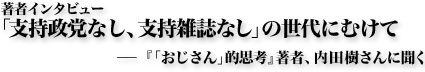|
■少数派の必要性
――内田さんは、この本の中で、日本が「変わり者」がいてもとやかくいわず、「均質化」することに過剰な圧力をかけない社会になってほしいと書いておられます。その箇所で、『「私一人『変』で、あとは全員『ふつう』」という状況では、人々がどれほど不寛容になるか、という事を経験的に熟知している。そのような経験を繰り返し味わってきた…』とありますが、読者として、それは具体的にどのような経験であったのだろう? と興味を持ちました。
いちばん古い記憶は五歳、保育園の時です。何もしていなかったのに、先生から「いたずらをした」ということで私も含めて三人が叱られたんです。居残りをして反省するようにと。誰もいない保育園に残されて、他の二人はべそべそ泣き出して、結局先生に謝ったのですが、この二人はなぜ何もしていないのに、こんなに簡単に謝るのか、私には意味が分からなかった。それで「内田君は反省しましたか」と聞かれたので「全然!」と(笑)。その時、五歳でしたけれど、もしかして私は変わり者なのではないか、と思ったんです。
その場のルール、みんなが「とりあえずこれで行きましょう」というルールがありますね。それに対して、自分自身ちゃんとした納得がいかないと、どうしても体がいうことをきかないんです。集団の中にいて、99%の人が同じ方向に行っている時、自分だけは「違う」と思うことがもの凄く多いんですね。でも、そういう時、不思議と孤立感はないんです。「僕のほうが正しい」と思うわけです。「そのうち、みんなも気づくだろう」と。
だから、悲壮感のない孤独なんです。修学旅行に行って、ひとりだけさっと着替えてお風呂に入ると、大浴場に「僕ひとり」ということってあるでしょう。いずれどやどやみんな来て、ごったがえしてしまうけれど、いまは「僕ひとり、貸し切り状態」って気持がいいじゃないですか。
だから、子供の頃から孤立していることが多かったです。
小学校でも、マジョリティーを形成して、その真ん中で親分のようにワアワアやっているか、たった一人で孤立しているかのどっちかでしたね。何人かで集まって小さな「仲良しグループ」でまとまる、ということはほとんどなかった。グループの中心にいるか、一人でいるか、のどちらかでした。
グループの中心にいる時というのは、僕にたいして非常に理解を示してくれるパートナーがいて、「内田はこういうことが言いたいわけよ」とまわりに説明してくれる、僕と一般世間の間の通訳をしてくれるんです。
――もしもクラスのみんなが内田さんのことを正しいと言ってついてきたら?
もしそんな事が起こったら、それは間違っている!(笑)絶対に絶対に間違っている。お前等おかしい!と言うでしょう。そういう時は、自分の言っていることがおかしいと思うはずです。
いままで自分の意見というのは常に少数派でしたから、それで安心していたんですが、自分の書いた本が売れてきて、僕の言うことに対して「まったく同じ意見です。」という人が次々と出てくると、なんとなく不安になりますね。安心するのではなくて、もしかすると自分の言っていることは間違っているのではないか、変なことを言っているのかもしれない、と。これまでの経験からして、そんなに多くの人に受け入れられる事を言っているはずはないから。
少数派というのが必要だと思うんです。政治的な機能としても、少数派は集団のバランスをとる役割を果たすものだと思っているわけです。この本にも書きましたが、システムというものが安定的に機能するためには、ある程度いろいろな考え方がニッチにばらけていたほうがいい、と直感的に感じるんです。全員がわあーっと同じ方向に向かっていくというのは、システムとして非常に危険なことだと思います。それを反対側に引っ張る力、拮抗する力が働いているときのほうが、システムは安定するし、健全に正確に機能する。
■「正解はない」という考え方
僕は合気道をやっているのですが、武道の身体運用で一番面白いところは、同じ方向に同じ力を使うと力が出ないということです。
たとえば日本刀の斬りの場合、「右手は遠くへ刀を投げ、左手は柄を引き寄せる」という相反する力を同時に使う事によって、非常に斬りの冴えが良くなる。両手とも押す、あるいは両手とも引くのでは、刀というのは全然切れないわけです。
人間の体も同じ。合気道で、相手が打ってきたのを押し上げるときには、相手の力に対して、体全体が同じ方向にむかって、一致協力して押し上げるよりも、たとえば左下半身は落として、右手を押し上げるほうが大きな力がでるんです。これは武道に限らず、身体運用における非常にベーシックな原理なんです。相反する二つの力が一つのシステムの中で同時に作用するとき、そのシステムそのものがものすごいエネルギーを放出するんです。バレエや仕舞のもたらす美的緊張感というのも、本質的にはそういうものだと僕は思ってますけど。
この本の全体を通じて書いているのは、そのようなことなんです。複数のファクターを同時に容認しておいて、そこでバランスをとるというのがいいね、ということです。
今のパレスチナ問題における批判の構造にしてもそうですが、どっちが正しいのか、どうすればいいのか、「正解がある」と考えていたら、身動きできない、むしろ「正解はない」と考えたほうがいい。いろいろなファクターがあって、それをどうやって上手く調整していくかが問題なのであって、誰が正義であるか、という議論で黒白をはっきりさせようとしているかぎり、それは永遠終わらない、死人が増えるだけです。万人が納得する解決策、単純明快な判断を下すことが、何よりも優先するのだ、という考え方はぜったいやめたほうがいい。
いろんな水準で同じ事がいえると思います。個人として考えた時も同じです。僕は、一人の人間のなかには複数の人格がいたほうがいいという意見をもっているんです。人格のシステムのためには、単純な裏も表もないキャラクターではなく、相互に矛盾する人格、良い面と邪悪な面、天使的な面と悪魔的な面、だらけた面と勤勉な面、という相反する要素を同時に自分の中に飼っておいて、それを時々に拮抗させながら使うほうが、生きていく上で能率がいい。
ある種の緊張関係を持つということ……それを、前の『ためらいの倫理学』という本の中では、「ためらい」という言葉で表現しました。複数の要請の中に引き裂かれた状態を、不幸な、緊張を強いられている状態とはとらずに、むしろ引き裂かれてある状態のほうが、可能性が開けるのではないか、と。
『ためらいの倫理学』のときには、そのことをいささかパセティックな感じで受けとめていました。「当為」と「欲望」、「本質」と「実存」のあいだに引き裂かれていて、どちらかに片づけ難く、ふたつの要請の間で必死にバランスをとっている状態こそが人間として正統なあり方である、というふうな書き方をしてしまったのです。
でも、そのあとよくよく考えてみたら、中間的な状態にバランスを保っているというのは、単にシステムとして「開かれている」というだけでなく、けっこう「気持がいい」のではないか、と最近思うようになってきました。
■バカにされているポジションは良いことだ
競合するさまざまなファクターが、共存しながらシステムとして安定しながら支え合い、刺激し合ってゆくというのが人間にとってというか、生物にとってはいちばん自然なあり方なんです。でも、このいちばん自然で気持のいい社会システムをどうやって構築し、管理してゆくかについて、整合的に語った社会理論というのは存在しないんです。
どんな社会理論もすべて、なんらかの静止的な状態、安定した状態、最終的な「理想状態」を描き出してしまうんです。…たとえば「イデオロギーの終焉」であるとか、「歴史の終焉」であるとかを書いた人はいますが、不均一なものがすべてひとつにおさまって、シーンとなって、動かなくなって、みんなが同じことを毎日繰り返すようになることが歴史の目標なのだという。それはウソでしょう。どう考えても、人間はずっと変化しつづけるにきまっています。変化し続けるということを前提にして、変化し続ける人間の集団というものの最低の法則性をみておいて、どうしたら一番コンフリクトがなく、矛盾のなかでも人が苦しんだり死んだりということがおこらないようにするにはどうしたらいいのか。矛盾というのは絶対になくならないし、対立もある、絶対に折り合わない多様性というものもある。それをなくすことなく、多様性のなかから引き出しうる最適性、利益の最大値を取り出すにはどうすればいいか、ということを考えることは、社会理論としてすごく重要だと思うんです。だけど、そういうことをいう人はいないんです。
この本にも書きましたが、憲法九条と自衛隊というのが拮抗する関係にあって、それによって戦後日本が戦争をしていない状態が維持されている、と思うんです。先進国のなかで57年間戦争をしていないというのは日本だけですから、戦争に関していえば、日本はもっとも成功している国なわけです。にもかかわらず、それを成功している、と言う人はいない。良くないことだ、どっちかに片づけよう、と。憲法を改正するか、自衛隊を廃止するか、どっちかにすべきだ、という議論の立て方自体が間違っているという当たり前のことを誰も言わない。現に日本は成功しているのに、成功していると言わない、失敗している、日本は国際社会の中で孤立している、恥ずかしいと言うんです。
――憲法九条と自衛隊という矛盾を抱えているということにしてもそうですが、私がいちばん感じたのは、つくづく日本というのは世界の中でも特殊な国なのだな、ということでした。私は無責任にも、それでいいのではないかと思ったんです。日本って、こういう国なのよ、と。一番最初、アメリカがテロ組織への報復に際して、協力国として日本が頭数にも入っていなくて、相手にもされていなかったことは、むしろ大変良いことであって、そのことを屈辱に感じる必要はまったくないと。こう言うのも何ですか、どうせ、バカにされているんだから…と。そう感じている人は、私は沢山いるはずだと思っているのですが…。
そういう意見はメディアには出てこないですよね。僕の読んだ限りでは、大塚英志と崔洋一のふたりが、相手にされなくていいじゃないか、と言ってますね。バカされているポジションというのは大変に良いことであると。この意見が実際はみんなの本音だと思うんです。これがマジョリティとなって、上手く言葉にならない本音のところを、ちゃんと理論化していって、これは一般的な理論として正しいのだ、と。ちょうど阪神が開幕7連勝したのと同じように(笑)、日本は戦争をしない57年目を迎えているのだから、人類未踏の記録を伸ばしていきましょうよ。そのほがずっと価値がある。アフガンに自衛隊を送って、アメリカによくがんばったなどといわれることと、このまま戦争をしないという記録を60年70年とのばしていくのと、どっちが世界史的にみて大事な事なのか、そんなの見えてるじゃないですか。とにかく、先進国の中で1945年以降、兵隊が外国にいって人を殺していない、というのは日本だけなんですから。なぜこれを誇らしく語らないのか。左翼の中にはそのことを評価している人もいますが、それでも自衛隊があるのはダメだ、と。起こらなかった事については論証できませんが、例えば、自衛隊があることによって防がれていたこともあったのではないか。そういう軍事的なプレザンスがある程度抑止力としては機能していたのではないかと思うんです。
■個人と集団は絡み合っている
もともとは僕は軍隊というものを嫌っていたのですが、何年か前に個人的に若い自衛隊員の人と知り合ったことがあって、これが、さわやかな、とても感じのいい青年なんです。特殊な教育を受けたからそうなったのかもしれないけれど、非常に礼儀正しくて、真率で、気配りが出来てて、目が清々しい。いまどき見たこともないような、ちょっと遠いところを見るような目をしているのです(笑)。想像でしかありえないことですけれども、もしも実際に戦闘がおこった時、自分たちがまず前線に出ていって、市民を守るために危険な任務を負うということへの自負心のせいではないかと。ちょうど「自分さえよければそれでいい」というエゴイストな若者の対極にある自負心ですね。とにかく、普通のサラリーマンなどではお目にかかれないような、とことん爽やかな青年なんです。
――それが自衛隊があってよいという理由にはなりませんが(笑)。
(笑)おっしゃるとおり、水準が違いますから。自衛隊は政治的な水準で語るべき問題で、いまの自衛官の印象はまったく個人的なものです。でも、水準が違うところで違う印象を持つというのは大事なことだと思うんです。たとえば、外国人に対してでも同じ様なことがありますね。包括的なアメリカ国民、新聞報道だけでしかアメリカ人を知らなかったら、僕だって「こいつら、世界最低」と思いますが、実際の知り合いの中にいるアメリカ人というのは、みんないい奴なんです。個人的につきあうことがないかぎり、その国の人に対する印象というのはとても限定的なものになってしまう。政治単位とその構成員ひとりひとりは違う、どちらかがどちらかを決める、というのではなく、両方みていないといけないと思うんです。個人が集団を代表するわけではないし、集団が個人すべてを代弁するわけでもない。でもやはり絡み合っている。
うちの学校にも中国から毎年客員の先生が来ますが、その一人が12億の中国人を代表できるはずもないのですけれども、話をしていると、やはりその人は「中国人は」という言い方をするし、「内田さんは日本人としてどう思うか」と問われる。そういう時、お前がいつ日本の代表になったのか、と言われそうですけれども、差し向かいで個人が話す場合でも、集団の一員としての責任を背負う。それはそれでいいと思うんです。
たとえば彼が「中国人はこう思っている…」と言った場合、あなたには中国人の代表として語る資格などない、12億分の1じゃないか、君の意見は君の意見だ、とは言えないわけです。
逆に、僕には日本人を代表して、中国の人に対して日本の戦争犯罪を謝る資格や義務や権利があるのか、ということになると、たしかに1億分の1の権利しかないわけです。でもだからと言って、「これはあくまで個人的意見にすぎません」とは言い切れないわけです。僕個人の意見なんだけれど、それを中国の人は個人の意見ではなく、日本という政治単位を代表する意見として聞いてしまう。それはやめてくれ、と言うわけにはゆかないんです。そういう場合は、やはり個人としてではなく、日本国民の代表として、中国国民を代表するあなたに対して、過去の戦争犯罪について許して下さいと謝る、ということが起こるわけです。そういうことは必ず起きてしまうんです。そういうかたちで個人と集団というのは、非常に錯綜しているんだと思います。
■日本人の美意識と長嶋茂雄
――いま、普通の生活の中で日本国民であることを意識する、ということはなかなかないと思います。私自身の経験でいうと、祖母の家に額に入った御真影が飾ってありました。それは天皇陛下と皇太后の写真に手彩色をしたものを複製したポスターだったのですが、それをたまたま額から取り出して見た時にはじめて、それが大変にチープな複製品であったことに気づいたんです。そうするまでは、その紙切れがものとしてどういうものであるかということにまったく考えがおよばなかった。もし描かれているのが天皇でなければ、あそこに飾られているものは何だろうか?写真なのか、絵なのか、複製なのか、オリジナルなのかと私は必ず思ったと思うんです。額に入って飾られているものを見たとき、それが美術品であるのかキッチュであるのかを確認しようとする思考が止まっていたんです。それはただ天皇陛下だった。その時にはじめて、それを額に入れて飾る祖母と同じ感性が、自分の中にもあるのだなあ、ということを感じておどろいたことがあります。
そのように、政治性というのは、本来、濃密に日常的な経験とか身体的な経験の中に入りこんでいるものでしょう。特に、天皇制の問題なんていうのは、ものすごく不思議な形で日本人の中に入りこんでいる。これは、三島由紀夫が『文化防衛論』で大胆に言い切っていたことですが、日本人にとっての美意識というのは全部天皇につながっていると。だから日本の美を守るためには天皇制を維持していかなくてはならないというロジックを展開するんです。このロジックは論理的には倒錯しているんですが、美意識と天皇制の間につながりがある、という前提の部分については、三島の指摘する通りなんです。
日本的な美意識――無常、幽玄、花、空、間……といったものを繰り返し確認していく課程で、天皇制的な政治性、天皇制を支えていたある種の感受性みたいなものが強化される、というのは間違いないです。たぶん、本質的なところで、日本文化の根本には、たおやかさや、ある種の女性性みたいなものや、すべてを受け入れてしまう包容性のようなものがある。ヨーロッパ的な、実定的でポジティブなものを重ねてゆき、あらゆる隙間を埋め尽くしてゆく、という文化ではなく、空虚さに社会や人間の実質があるというような考え方が、日本人の美意識の内には抜き難く入り込んでいるんですね。絵画にしても、音楽にしても。三島由紀夫的にいうなら、それは政治性の中核に空虚がある、ということになる。天皇というのはすべてを受け入れる女性原理である、と。
天皇的キャラクターというのがあるじゃないですか。たとえば日本人がもっとも好きで、誰もその人の悪口が言えない、という人。たとえば長嶋茂雄。
あの人はすでに半世紀にわたってスターでいるわけですが、彼の悪口を言う人というのはもうみごとに一人もいないわけですよね。これはちょっと異常な事態だと思いませんか? 誰からも悪く言われない人って。どうしてそういうことが起こるかというと、長嶋さんはたぶんその中核に非常に虚ろなものを抱え込んでいるからなんだと思います。真ん中に核がない、空虚なキャラクターです。
何のために野球をやるのか、ということについて、あの人はたぶん何もわかっていない。お金が欲しいだとか、名声が欲しいだとか、すぐれた運動能力によって自己実現をしたいだとか、そういう雑なものが何もなくて、目の前にポンとボールが飛んできたから打つ、捕る、ただそれだけなんです。普通に考えて「意味があること」のために野球をやっているわけではないんです。ボールが飛んでくる、ボールに身体が反応する、ああなんて気持がいいんだろう、という純粋な快感だけで成り立っているキャラクターですよね。だから、その快感が観客にストレートに伝わってくるんですよ。ボールゲームに興じている長嶋茂雄自身の快楽がそのまますっと観客にパスされる。だから、長嶋茂雄を見ているときに観客はすごく気持がいいわけです。その快楽は、他の選手の活躍を見ているときの快楽とは次元が違うんです。彼は空虚なんですよ。彼が空虚な通路だから、彼を媒介として、観客はボールゲームの本質に全面的に、直接的に触れることができるわけですよね。ああいう無欲無心の人というのが、日本人のもっとも好きなキャラクターなんです。
■内面のない存在
他にも、たとえば『男はつらいよ』の寅さんも日本人が非常に好きなキャラクターですよね。寅さんもまた、ある意味では中空の人ですね。定住することもなく、何も所有せず、自己実現すべきものもない、モノを売ってはいるけれど、香具師だから人が持ってきたものをただ売っているだけ、女の子もやってきては去っていく、すべては彼を「通路」にして、通過していくだけです。彼は、彼自体は何ものでもなく、いろんな人間たちのすべてを統合する「クッションの結び目」ですよね。彼がいるおかげであの物語に出てくる全員が共通の記憶を共有していて、それによって、彼を中核にしてリンクされて、ひとつの物語世界を作っている。ああいうのが日本人は大好きなわけです。
他にも例があると思いますが、長嶋さんや寅さんのようなキャラクターが、アメリカやフランスで満場一致的なポピュラリティーを獲得するなんてちょっと考えられないでしょう。そういうものは、これからも受け継がれていくと思うんです。美意識というのか、イデオロギーというのか判らないですけれど、そういうのが「好き」という日本人のメンタリティーは変わらない。そういうメンタリティーを持つことをやめろといってもしかたがない。現に日本人の社会組織というものは、長嶋や寅さんといった「天皇型キャラクター」を軸にして組織化されているときがいちばん気持がいいし、効率的に動くわけですから。そういうものを社会的な統合のための原イメージとしているという事実をまず踏まえて、そこから社会理論を立ててゆくという方向に頭を使わないとだめなんじゃないですか。
――そういうキャラクターは、この本の最後の夏目漱石論「『大人』になること――漱石の場合」で触れておられた『虞美人草』の登場人物・宗近君にも通じますね。
そうですね、内面のない存在。夏目漱石が近代の日本人のモデルを作るさいに、伝統的な人物造型の中で、おそらくもっともこのパターンを日本人は好きなのではないか、これで「近代的な日本人」の理念型ができるなら、それでいきましょう、ということで作り上げたものだと思うんです――これは私の理論ですけれど。「坊ちゃん」と「宗近くん」は同じキャラクターですからね。
――単純に憧れますね。自分がもし長嶋監督のようなキャラクターであったらいいだろうなあ、と思います(笑)。たとえばそれが他の人物「浜崎あゆみのようになりたい」だったら、私というものがそこにはなくては意味がないのかもしれませんが、長嶋のようになれるのだったら、自分の内面なんてものはどうだっていいと思います。
(笑)。国民全員が長嶋みたいだったらいいなあ、ということなんでしょうね、日本人の意識としては。
――本当に、そうですか?(笑)
みんななったらいいと思いますよ。そうなってほしい。つまり、ロールモデルなんです。たぶん外国では、こういう事がないと思うんです。必ず難癖つける人間が全体の3割くらいはいるのじゃないでしょうかね。でも日本の場合は、そこに何か、ある種のたおやかさというか、優しさというか、底抜けの包容力というか、そういうものがある人には全員がどどっとなびいてしまうんですよね。社会的統合の中心に、底の抜けた人物がいるというのが、天皇制的な政治力学なんだと僕は思います。それはもう僕らのなかに入りこんでいる。これはバルトが『表徴の帝国』で書いていたことですけど、中心に底抜けのものがある社会、それが日本だ、と。
――では欲というものは? 欲はないと困りますよね?
どうなんでしょうね。もちろんあっていいでしょうけど、ある種の組織を動かしていこうとなったら、中心にいる人は基本的に欲をもってはいけない。私利私欲を持つのが人間として当たり前だ、といくらいっても、中核にある人が私利私欲を持つと、集団は崩壊しますよ。政治家でもそうです。我々にとって、政治家が集団の中核にいる人であるなら、その人は無欲でなくてはいけない。政治家自身もみんなと同じ一市民で、その中でとりわけ政治的な先見性のある人間だから政治をやっているんだ、政治家も人間なのだから経済行為をして何がいけないんだ、というロジックは通らない。社会を動かすために、求心力のある組織を作るために、主導権的な立場に立とうとするのなら、やはり欲は捨てなくてはいけない。すごく単純な事なのに、それを判らない人が多すぎる。……なんだか、本とは関係のない話ばかりしてしまいましたね。
■「おじさんメディア」の害悪
――では「おじさん」についてうかがいます。この本でいう「おじさん」というのはどのような人のことをいうのか、私にはこれといった人物が身近に思い浮かばなかったのですが…。
実際にそういう人が身近にいるかどうかは別として、ある種の理念として、日本の戦後を支えてきた、さまざまなファクターを全部統合してつくったこんな感じの人、普通のおじさんということです。日本の普通のおじさんというのは、なかなかこれといった像を結びにくい存在なんですよね。たとえばおじさん的メディア、『週刊文春』とか『週刊新潮』、『週刊現代』、『週刊ポスト』。そういうものを通して読むと、そこに浮かび上がってくるおじさんの像というのは非常におぞましいものになる。人のあら探しばかりしていて、お金儲けの事ばかり考えていて、健康に気を使って、頭の中はセックスの妄想でいっぱい、あとはギャンブル……というようなね。総括的にみると大変貧しい人物像しか浮かんでこない。ああいう「おじさんメディア」が紡ぎだしている「日本のおじさん」こそバーチャルなもので、それは実像とは大変違うものだと僕は思うんです。実際のおじさんというのは、ああいうメディアの描いている像と、自分自身との落差というのを非常に感じていて、なんでこんなところでまとめられちゃうんだろう、と思っているのではないか。
僕自身、もう10年くらい、定期刊行物というのはひとつもとっていないんですよ。雑誌の中で読む物がないんです。自分の関心に応えるもの、自分と意見が合うようなものというのが、日本のメディアの中には一つもない。何を読んでも不愉快になる、というか違和感を感じる。小学生の時に『文藝春秋』や『週刊新潮』を読んでいるときには、まったく違和感なんてなかった、内容に共感できなくても、そこで書かれていることは子供にはとりあえず関係ないからです。でも、いざ自分がその読者として想定されていると思って読むと、非常に違和感があるんです。僕みたいに、既成のメディアにはまるで共感できないな、と思っている人は沢山いると思うんですよ。だけど実際には、現に大量配布されているマスメディアの中では「これが日本のおじさんである」というイメージが頭から決められている。若い人たちも、そのイメージに合わせるように「おじさん」への自己改造を進めて行く……でも、既成のメディアにまるで共感できなくて、自分の意見を代弁してくれるメディアがない、と思っている人のほうが、僕らの同世代だったら多いと思うんです。「支持政党なし」というのと同じで「支持雑誌なし」だと。そういう人たちがたくさんいるのだよ、ということをいわんとした訳です。
――では、最後になりますが私がいちばん印象に残った箇所をお伝えしておきます。「文学」をして「矛盾する要請に同時にこたえるような存在をありありと現前させる方法」だというところです。最後の章、「『大人』になること――漱石の場合」にありました。普段「文学」について考えたこともなかったのですが、なるほどと思いました。
「文学」とは言わずに「物語」と言えばいいんです。哲学的な概念というのは難しい、なぜかというと、言い換えがきかないから。ひとことで説明しようにもできないのなら、「おはなし」にするしかない。「おはなし」の中である人がある現実の場面を生きていく、ということを具体的にイメージしていかないと、キーワードになるような概念について説明できないんです。ひとことで定義してもわからないものをわかるようにするために、「おはなし」というのはある。ひとつながりの一定の時間が進行してくるようなユニットをもってこないと、絶対に説明のつかないものがあるわけです。そのために人間は物語を語るわけです。僕が毎日たくさんのものを書くのは、基本的には理解したいからなんです。なにか自分に言いたいことがあって、それを皆さんにお伝えするためではないんです。たとえばある新聞記事に違和感をおぼえるとします。そのことを書いていくうちに、自分が違和感をおぼえたみちすじというのがわかってくる。最初から何か「意見」があって書きはじめるわけではない。じつは書き出す前は何もわかっていなくて、最後まで書いてみてやっとわかる、そういうものってあるじゃないですか。それが僕にとってはひとつの「おはなし」なんです。その「おはなし」を書かなければ、僕はそのことについて理解できなかった、ということ、「おはなし」を通して自分が何かを知るということです。書くというのは、自分の内面にあるメッセージを伝える、というのではなく、自分が何を考えているのか、ということを確認する作業なんです。自分が間違っている時は、文章に書くと変なんです。だから書くということは自己発見・自己修正のための大事な手続きだと思います。
|